
1回目は、10月15日に実施された東北電力(株)女川原子力発電所見学。清々しい秋晴れの空の下、参加者たちはバスに乗り込み、午前9時、仙台駅を出発しました。




 お楽しみの昼食は、旬の海鮮丼・海鮮料理を楽しめる女川海の膳「ニューこのり」で「欲張りこのり丼『海鮮』」をいただきました。なんと海鮮丼と穴子天丼の両方を味わうことができます。ふわふわの穴子の天ぷらに新鮮なお刺身で、お腹いっぱいになりました。
お楽しみの昼食は、旬の海鮮丼・海鮮料理を楽しめる女川海の膳「ニューこのり」で「欲張りこのり丼『海鮮』」をいただきました。なんと海鮮丼と穴子天丼の両方を味わうことができます。ふわふわの穴子の天ぷらに新鮮なお刺身で、お腹いっぱいになりました。


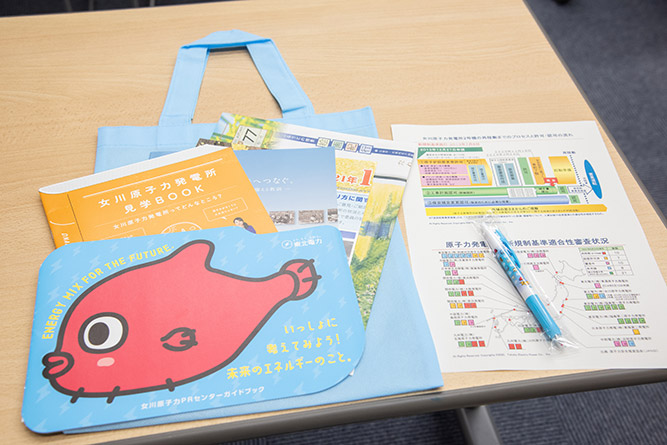 さて、いよいよ女川原子力発電所に向かいます。まず、「女川原子力PRセンター」でバスを降り、東北電力(株)女川原子力発電所で広報を担当する福地裕明さんから、現在の女川原子力発電所の状況や女川で東京電力福島第一原子力発電所のような事故が発生しなかった理由等について学びました。東日本大震災の時、女川原子力発電所は震度6弱の強い揺れの後、約13メートルの大津波に襲われました。しかし、運転中の1号機と3号機、それに原子炉起動直後だった2号機の全てが安全に停止し、今も安定した状態が保たれています。原子炉を安全に停止させるためには、原子炉を『止める』『冷やす』、放射性物質を『閉じ込める』ことが大切です。東京電力福島第一原子力発電所が、想定を上回る津波によって電源を喪失し、原子炉の冷却機能を失ってしまった一方、女川原子力発電所は、三陸海岸が大津波に襲われてきた歴史を考慮し、建設計画段階から津波対策を重要課題と位置づけていたそうです。敷地高さが海抜14.8メートルと高く設定されていたことや震災前までに機器や配管の補強など1~3号機合計で6600か所の耐震工事を終えていたことが事故を防ぐことに繋がりました。
さて、いよいよ女川原子力発電所に向かいます。まず、「女川原子力PRセンター」でバスを降り、東北電力(株)女川原子力発電所で広報を担当する福地裕明さんから、現在の女川原子力発電所の状況や女川で東京電力福島第一原子力発電所のような事故が発生しなかった理由等について学びました。東日本大震災の時、女川原子力発電所は震度6弱の強い揺れの後、約13メートルの大津波に襲われました。しかし、運転中の1号機と3号機、それに原子炉起動直後だった2号機の全てが安全に停止し、今も安定した状態が保たれています。原子炉を安全に停止させるためには、原子炉を『止める』『冷やす』、放射性物質を『閉じ込める』ことが大切です。東京電力福島第一原子力発電所が、想定を上回る津波によって電源を喪失し、原子炉の冷却機能を失ってしまった一方、女川原子力発電所は、三陸海岸が大津波に襲われてきた歴史を考慮し、建設計画段階から津波対策を重要課題と位置づけていたそうです。敷地高さが海抜14.8メートルと高く設定されていたことや震災前までに機器や配管の補強など1~3号機合計で6600か所の耐震工事を終えていたことが事故を防ぐことに繋がりました。


 また、PRセンターでは、アテンダントの方から2分の1サイズの原子炉模型や高さ4メートルもある実物大の燃料集合体・制御棒の模型を使って、原子力発電のしくみなどについての説明を受けました。
また、PRセンターでは、アテンダントの方から2分の1サイズの原子炉模型や高さ4メートルもある実物大の燃料集合体・制御棒の模型を使って、原子力発電のしくみなどについての説明を受けました。
最初の目的地となる「女川町まちなか交流館」までは、約1時間半の道のりです。
まずは、バスの中で、参加者のみなさんから自己紹介をしていただきました。仕事やプライベートで女川と関わりのある方もおられましたが、「原子力発電所を見学する機会はなかったので、楽しみにしていました」など、セミナーに参加する目的や意気込みを語ってくれました。



震災で甚大な被害を受けた女川町は、防潮堤を作らず、町全体を嵩上げする独自の「復興まちづくり」を進めています。午前10時半、女川のまちなか交流館に着いた参加者たちは、語り部ガイドを務める女川町観光協会の阿部真紀子さんから、震災時の状況や復興のあゆみについてお話を伺いました。地元で生まれ育った阿部さんは、スクリーンに震災前後の写真を映し出しながら、時折、参加者に語りかけます。以前は女川原子力発電所を意識することはあまりなかったけれど、震災時に避難所となったことで、身近に感じるようになったことも話して下さいました。
参加者は力強く進む女川の復興の様子に強い印象を持たれたようでした。




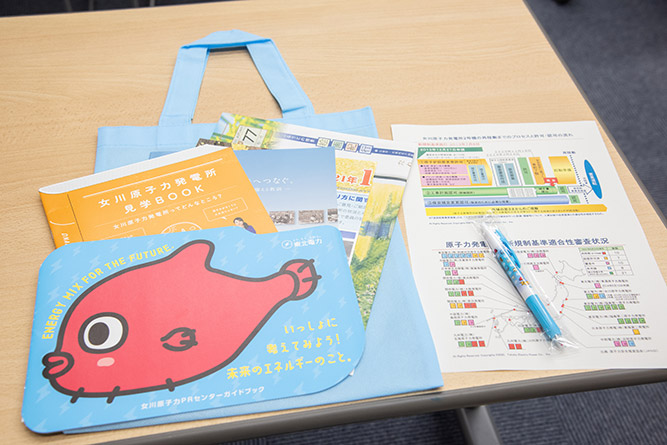



また、エネルギーミックスコーナーでは、日本のエネルギー自給率はわずか12%しかないこと、電気を安定して届けるためには、安全の確保を大前提に、原子力、火力、再生可能エネルギーなどをバランスよく組み合わせて発電する「エネルギーミックス」の実現が必要なことなどを学びました。




